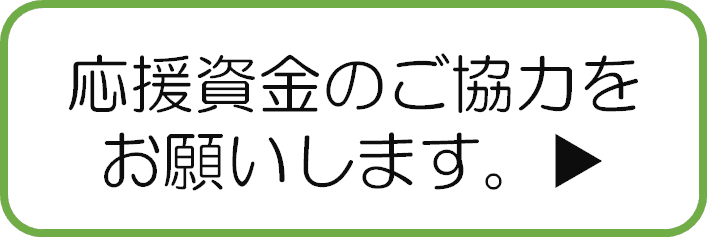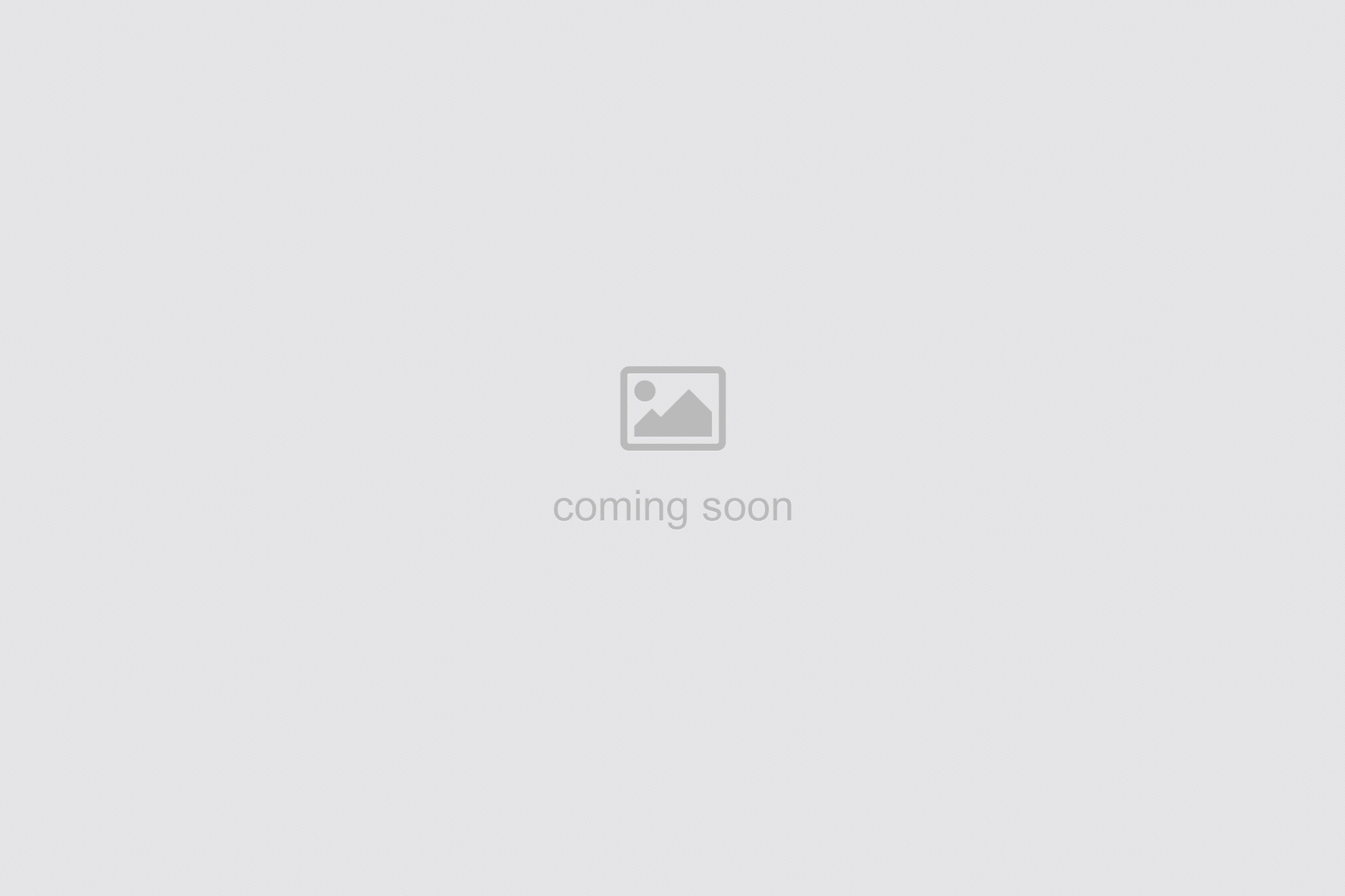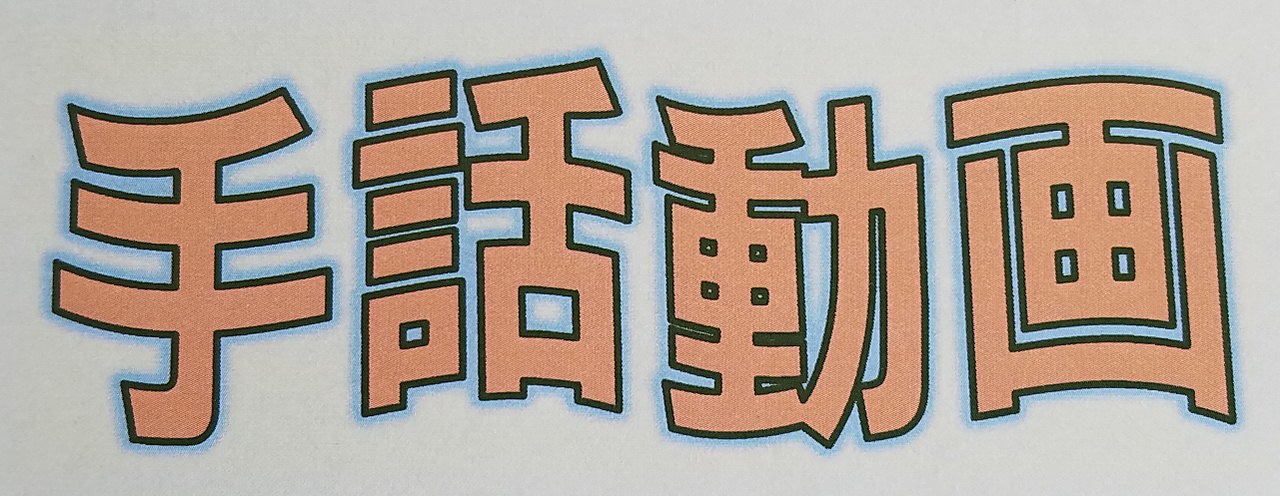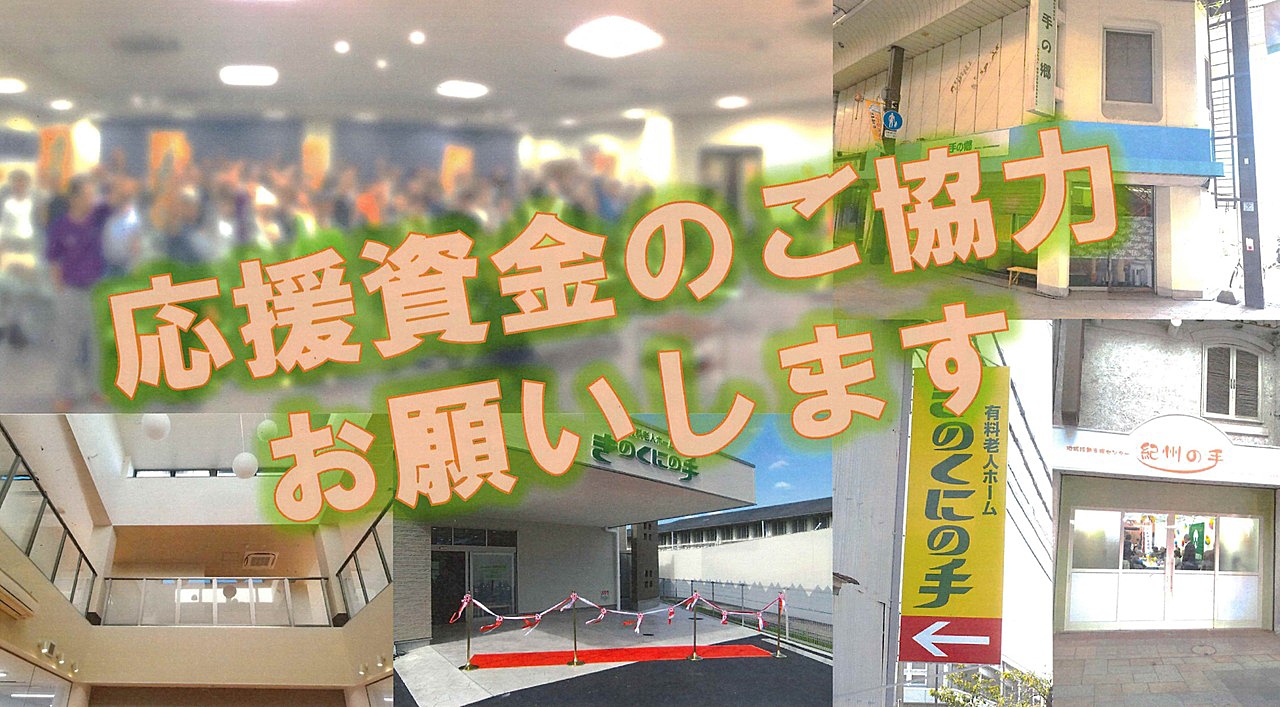本会について(あゆみ)
あゆみ(沿革)
| 1922年(T11) | ・日本聾唖協会和歌山部会発足 |
| 1946年(S21) | ・戦争により自然消滅された和歌山ろうあ協会を再建 近畿地区では3番の組織再建 |
| 1950年(S25) | ・「和歌山県聴覚障害者福祉協会」と名称を変更 |
| 1952年(S27) | ・「和歌山県聾唖協会」に改称 |
| 1956年(S31) | ・県組織の「和歌山県ろうあ連盟」に改名 和歌山市組織である「和歌山市ろうあ協会」に分割される |
| 1958年(S33) | ・「和歌山県聴覚障害者協会」に改称 |
| 1970年(S45) | ・和歌山市に県内初の手話サークル「たんぽぽ」誕生 |
| 1972年(S47) | ・和歌山の機関紙 「きのくに」初発行 |
| 1974年(S49) | ・和歌山県庁に手話通訳者を配置 和歌山では初 |
| 1975年(S50) | ・第9回全国ろうあ青年研究討論会 かつらぎ町にて開催 ・和歌山ろう者の生活と権利を守る会など聴覚障害関係8団体とともに「ろうあ会館建設要求運動」開始 |
| 1976年(S51) | ・県議会への「聴覚障害者総合福祉会館建設請願署名運動」開始 県議会へ47,000余の署名を添えて請願。県知事にも会館建設を 陳情 |
| 1977年(S52) | ・和歌山県聴覚障害者協会初代会長 村井七郎治氏逝去 |
| 1978年(S53) | ・県議会で「県聴会館建設請願」が「条件付」の不採択となる |
| 1980年(S55) | ・「第31回近畿ろうあ者大会」を和歌山で開催 和歌山県聴覚障害者協会の手話劇「父帰る」が評判となる |
| 1981年(S56) | ・「第14回全国手話通訳問題研究会」(長野市)で 手話劇 「父帰る」を再演 |
| 1982年(S57) | ・国際障害者年を記念して「第1回耳の日記念のつどい」を開催 ・機関紙「きのくに」月刊化 |
| 1983年(S58) | ・機関紙「きのくに」が第3種郵便物に認可される |
| 1984年(S59) | ・県事務所の非常勤嘱託手話通訳の「身分と生活の保障」及び 「常勤化」を 求める2つの「県議会請願署名運動」開始 県議会へ23.700余の署名を添えて請願 ・和歌山市に福祉タクシーを制度化 |
| 1985年(S60) | ・「県議会請願署名」により県事務所の非常勤嘱託手話通訳の待遇が 3万円のアップに改善される ・「第4回耳の日記念のつどい」を御坊市で開催 以後、県下4ブロックの輪番制となる ・県聴障協の専任職員を採用 四畳半の「仮事務所」で業務スタート 和歌山市中之島に2階建て民家を借りて専用事務所を確保、オ ープン ・手話通訳の制度化を目指して「アイ・ラブ・コミュニケーション」 パンフ普及運動がスタート ・和歌山市に福祉タクシーを制度化 |
| 1986年(S61) | ・県立和歌山ろう学校に「校歌」ができる ・「アイ・ラブ・コミュニケーション」普及数が目標以上に達成 |
| 1987年(S62) | ・「理容部」新設 ・全国ろうあ者大会(釧路市)で「パンフ普及運動」の評価を得て 「61年度の活動に優れた団体」として全ろう連から表彰される |
| 1988年(S63) | ・機関紙「きのくに」が第100号に到達 ・消防署などへの「ファックス」設置ひろがる ・「社団法人」化を目指して「法人設立決起集会」を開く ・県聴覚協事務所が県身体障害者総合福祉会館内に移転 |
| 1989年(H元) | ・「政見放送に手話通訳挿入を」と県選挙管理に要望書を提出 ・県聴覚協 第9代会長 佐武一郎氏が聴障者では2人目の黄綬褒章を 受章 |
| 1990年(H2) | ・初の「手話通訳士」試験に3名が合格 |
| 1991年(H3) | ・字幕入りビデオライブリー貸出事業開始 ・県内初の聴覚障害者の「ホームヘルパー」が誕生 ・県内初の聴覚障害者の地方公務員が誕生 ・法人への願いに燃えて「社団法人設立総会」開催 「社団法人」を県知事から許可される |
| 1992年(H4) | ・田辺市と新宮市に手話通訳者を設置 |
| 1993年(H5) | ・有料道路割引 開始 ・「第41回全国ろうあ者大会」を白浜町で開催 |
| 1994年(H6) | ・「みんなでめざそうよりよい手話通訳」のパンフ普及運動を行う |
| 1995年(H7) | ・「第7回ろう教育を考える全国討論集会」を高野山で開催 |
| 1996年(H8) | ・「和歌山・聴覚障害教育を語る会」を発足 ・機関紙「きのくに」第200号に到達 |
| 1997年(H9) | ・和歌山県聴覚障害者の設立50周年記念会を岩出で開催 ・重複障害者の民間授産施設「くじら共同作業所」が和歌山市にオープン |
| 1999年(H11) | ・「情報提供施設」オープンへの具体的な動きが始まる |
| 2000年(H12) | ・県身障連会館内で「和歌山県聴覚障害者情報センター」オープン(身障連が運営) |
| 2001年(H13) | ・第35回全国ろうあ者体育大会を和歌山市で開催 |
| 2002年(H14) | ・携帯「メール110番」スタート |
| 2004年(H16) | ・国の三位一体改革を受け、県・市町村へ要望を出す |
| 2005年(H17) | ・障害者自立支援法に対する県内に6団体と組んで対策本部を設立 ・障害者自立支援法 成立 |
| 2006年(H18) | ・障害者自立支援法 実施 ・「県立和歌山ろう学校の名称(存続)や寄宿舎の在り方をそのままで」の署名活動を開始し、一ヶ月で一万余の署名を集め県教育委員会に提出 ・和歌山県聴覚障害者の設立60年記念大会 開催 |
| 2007年(H19) | ・特別支援教育制度が施行 |
| 2008年(H20) | ・20ヶ国批准で障害者権利条約が発効 |
| 2009年(H21) | ・内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置 ・映画「ゆずり葉」上映会を県下5カ所で開催 (観客数:全国5番目) |
| 2010年(H22) | ・8団体が集結し障害者制度改革推進和歌山本部を設置 |
| 2011年(H23) | ・「We Loveコミュニケーション」パンフ、署名の目標数達成 ・社団法人から一般社団法人への移行承認を得るために、12月4日に臨時 総会を開く ・「手話言語法」パンフ販売の目標数を達成 |
| 2012年(H24) | ・4月1日、一般社団法人への登記(移行)設立 ・当会のホームページ開設 |
| 2014年(H26) | ・3月24日より、支部事務所(岩橋)を開所 ・手話言語法制定に向けて県内の全て市町村議会において意見書が採択! |
2015年度(H27) | ・第15回全国障害者スポーツ大会が44年ぶりに和歌山にて開催される ・和歌山市手話言語条例制定に向けた意見交換会が開かれる ・在任中の馬場正義副会長が事故により急逝 ・県内初、聴覚障害者向けの地域活動支援センター「紀州の手」を開所 |
| 2016年度(H28) | ・障害者差別解消法が施行される ・和歌山市手話言語条例、和歌山市障害者差別解消条例が可決され、4月1日より施行 ・当協会初の運営下で就労継続支援B型「手の郷」を開所 ・聴覚障害者情報センターにろう者職員を配置(非常勤…1年間) ・当協会創立70周年記念集会を開催し、140名が集う ・手話を広めようフォーラムを和歌山市内において開催。 鳥取県知事 平井伸治様が来和。 |
| 2017年度(H29) | ・4月1日、視聴覚障害者情報提供施設がビッグ愛に移転 同時にろう者を正職員として雇用 (指定管理者…県身障連)
当協会も本部事務所(駿河)をビッグ愛6階に移転(岩橋事務所は閉鎖) ・関係団体と共に視聴覚障害者情報提供施設の指定管理者公募に対して運動を本格化(次回の公募の際、視覚と聴覚を別々に公募することを要求運動) ・当協会青年部創立50周年記念集会を開催 ・12月19日「和歌山県手話言語条例」が制定(施行12月26日) |
| 2018年度(H30) | ・ろうあ老人ホームへの資金作りチャリティーイベント 「現代国際巨匠絵画展」を開催(売上1200万円の一部を資金支援) ・第4回世界ろう連盟青年部 子供キャンプinアルゼンチンへ リーダーとして和歌山の青年部(田村大希氏)とろう子どもが参加 ・第68回近畿ろうあ者大会を和歌山ビッグウエーブにて開催 ・住宅型有料ホーム「きのくにの手」開所 ・「加納の手」デイサービスセンター開所 |
| 2019年度(R1) | ・聴覚障害者情報センター所長にろう初の福田政和氏が就任 ・視聴覚障害者情報提供施設の指定管理者募集の方法(「視聴覚」一本ではなく「視覚」と「聴覚」二本立て)に対して16114筆の署名を議会議長、副議長に提出 ・第31回全国ろうあ高齢者大会・スポーツ大会を和歌山にて開催 ・指定管理者の入札不調のため、二本立てによる再募集に「県聴覚障害者情報センター」を申請し、3月17日の議会において承認(選定) |
| 2020年度(R2) | ・4月より、県聴覚障害者情報センターの運営を受託開始(設置20年目で「当事者団体で運営」が実現) ・書面による代議員会を開催(新型コロナウイルス感染予防のため) |
2021年度(R3) | ・共同生活援助(障害者GH)「和歌の手」開所 |
2022年度(R4) | ・4月より、聴覚障害児支援中核機能モデルとして、県聴覚障害児の早期支援体制整備事業「乳幼児きこえとことば相談」を当協会が受託(当事者団体としての受託は全国初) ・3期目(2023年度~3年間)聴覚障害者情報センターの指定管理者募集に申請し、当協会が選定を受ける ・訪問介護「なごみの手」内に福祉・介護タクシーを事業開始 ・デイサービス「加納の手」に共生型生活介護を事業開始 ・手の郷の拠点を移転(本町から湊へ) |
2023年度(R5) | ・盲ろう者向け通訳・介助員養成・派遣事業を受託 |